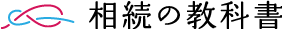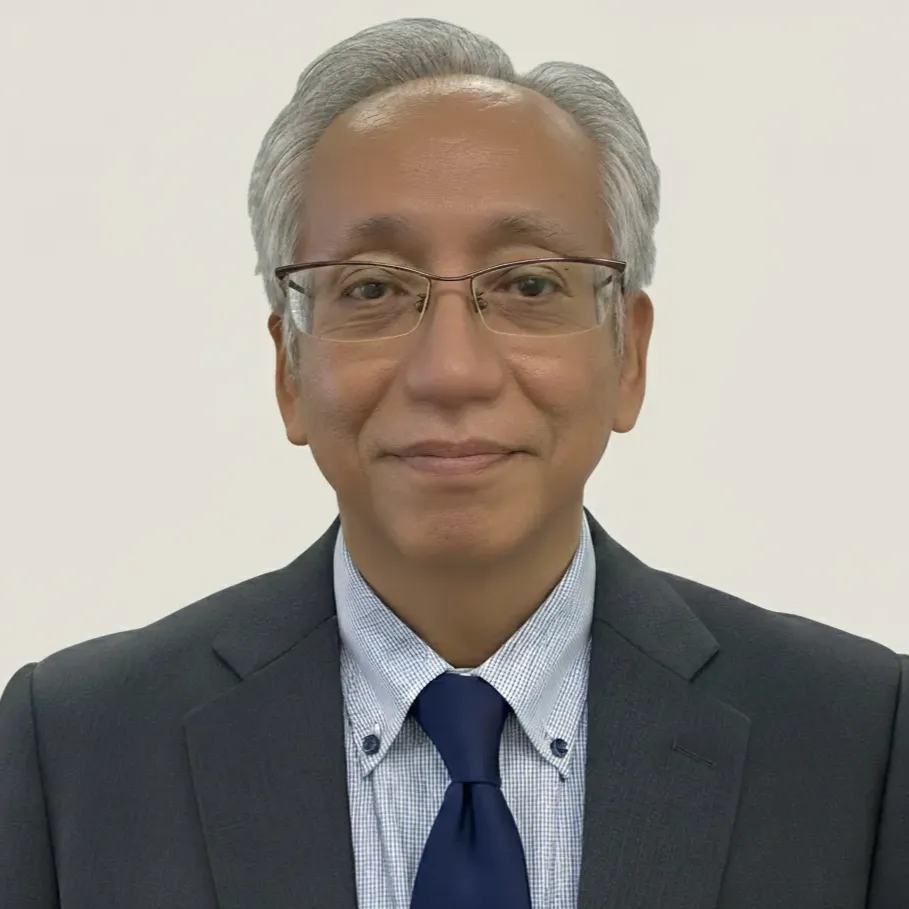遺言書の検認って何?相続前に確認したい申立手続きと注意点

自宅などで遺言書を見つけた場合、家庭裁判所で「検認」と言われる作業を行わなければなりません(公正証書遺言の場合には検認の必要はありません)。では、なぜ遺言書を見つけたときは検認が必要なのでしょうか。そもそも検認とはどういったことなのでしょうか。今回は遺言書の検認についてみていきましょう。
検認とは
検認とは、相続人に遺言の内容と存在を知らせる作業のことです。また検認には遺言書の偽造、変形を防止するという目的もあります。こういった観点から遺言書が見つかったとしても、その場で開けてはいけません。また、検認作業が終了していない場合は、不動産相続登記や銀行口座の名義変更などの相続手続きは出来ません 。このように検認は、必ず必要な作業のひとつです。
なお、検認は遺言の内容を判断するものではありません。そのため遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、遺留分の請求は検認の場では行えませんので注意が必要です。
どうやって検認を行う?
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所に検認をしてもらうように申し立てをします。この時に申し立てをするのは、被相続人の最後の住宅地を管轄している家庭裁判所です。相続人の管轄の裁判所に申し立てをしても、受け取って貰えませんので注意しましょう。申し立ては遺言を保管していた人、または遺言を発見した相続人が行います。
申し立てをするのに必要な書類について
検認の申し立てをするためには遺言書を作成した遺言者の生涯全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。検認の申立書などは裁判所のホームページからダウンロードも可能です。一番時間が掛かるのは、相続人全員の戸籍謄本を揃えることかもしれません。もし申請後、書類に不備がなかった場合には裁判所から相続人全員に検認の日が知らされます。この時に相続人全員が揃っていなくても検認は行われますが、申し立てた本人は出席しなければなりません。また委任を受けた司法書士や弁護士が立ち会っても良いことになっています。
検認当日の流れについて
検認当日は、出席者の立ち会いのもと遺言書が開封され、遺言の発見場所や筆跡等を確認します。検認終了後、相続手続きを行う際は検認済証明書の発行を申請します。不動産の相続登記や銀行預金の名義変更には検認済証明書の付された遺言書が必要です。
最後に
このように検認は必ず必要な作業です。しかも、裁判所からの検認の期日は半月から1ヶ月、長ければ2ヶ月くらい掛かる場合もあります。相続放棄の期間や相続税の申告は検認がいつ行われたかは関係ありません。遺言書が見つかった場合は速やかに検認の手続きを行うことをお勧め致します。