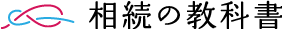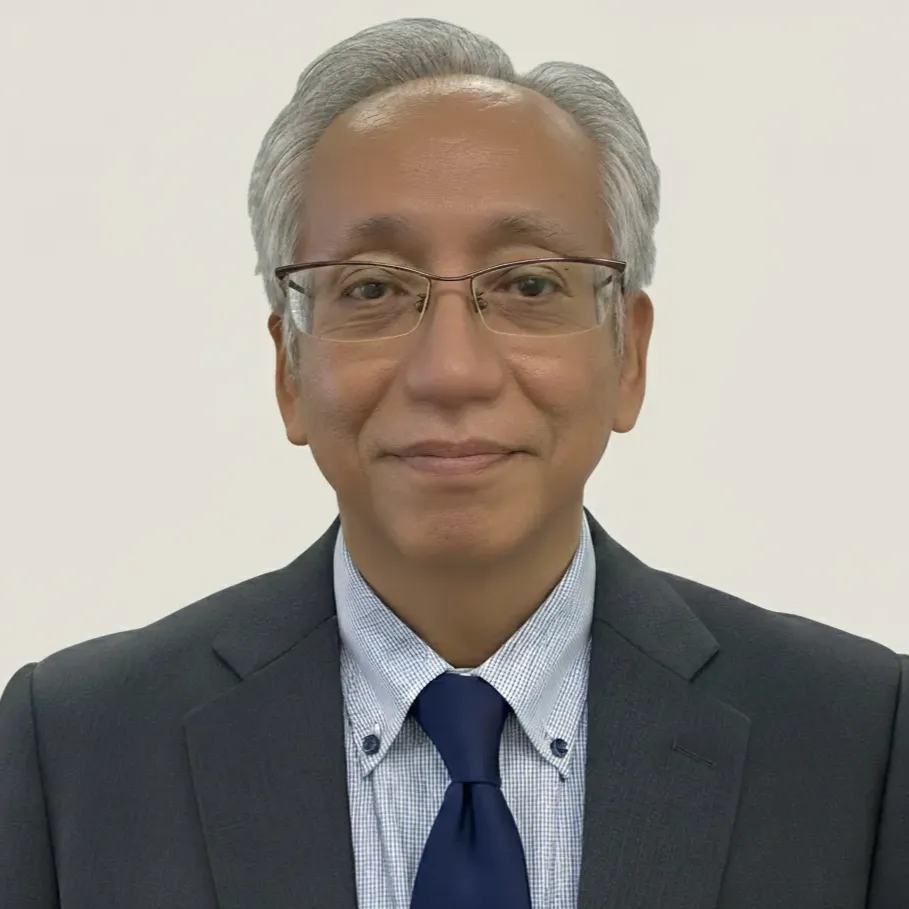相続手続きの基本から応用まで|失敗しない進め方ガイド

相続の手続きを専門家に依頼する方は多いですが、依頼をすれば、費用はもちろん発生します。費用面を考えると少しでも費用を抑えたいと考えることは自然なことです。では、相続人自身で手続きはできるのでしょうか。もちろん流れや手続きに関してしっかりと理解し、なおかつ期限までに実行できるなら手続きをご自身で行うことは可能です。
遺言書や相続人について
被相続人が亡くなる前に遺言書を作成し、専門家や銀行に預けている場合があります。相続が開始されたら、まずは遺言書があるかどうかを探してみましょう。また、相続人は戸籍謄本によって調査していきますが、遺産分割協議中や協議書作成中に相続人調査が不十分とわかると、それまで進めていた話が無効になります。そうならないように、被相続人の生まれた時までの戸籍を遡る必要があります。
財産調査について
財産に当たるものは現金や預貯金、不動産、有価証券、貴金属などがあります。被相続人が使っていた銀行や登記済権利書など家中を探す必要があります。また、借金も相続の対象になりますのでしっかりと調べる必要があります。
相続の承認について
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄があります。何も手続きをしなければ単純承認となり、借金も含めて全ての財産を相続します。全ての相続を放棄したい場合は裁判所に相続放棄の申述をします。プラスで得た財産を限度に借金などマイナスの財産を相続する場合は裁判所に限定承認の申述をします。。相続放棄、限定承認は相続の開始を知ってから3か月以内と期限が決まっています。相続放棄は一人からでもできますが、限定承認は相続人全ての人が行う必要があります。
準確定申告、相続税の申告について
被相続人が亡くなる日までの所得について、所得税の確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。計算方法は通常の確定申告と変わりはないのですが、相続の開始を知ってから4か月以内に行わなければなりません。さらに相続人全員の署名が必要となりますので注意が必要です。また、被相続人の財産の合計が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合は相続税の申告が必要です。配偶者の税額の軽減や小規模宅地の特例により相続税額がない場合も、申告はしなければならないのでしっかりと確認しましょう。
遺産相続協議書について
遺産分割協議書には決まった形式はないと言われています。ただ記入漏れや間違いがあった場合には、無効になる可能性もありますので注意が必要です。形式などの見本として司法書士などのホームページに載っている場合もありますので、参考にされてもいいでしょう。
遺留分侵害請求について
遺言書が認められた場合には、一部の相続人が法定相続分より多く受け取り、他の相続人は法定相続分より少なく受け取るケースもあります。ですが、民法で遺言に左右されない相続財産の最低限度の取り分が定められています。これを遺留分といい、相続した財産が遺留分を下回る場合は、金銭の支払を請求することができます。この場合、まずは遺留分権利者自身が、遺留分の権利を行使する旨の意思表示をしなければなりません。
最後に
こうして相続に関わることをみてみると、相続は被相続人の財産と相続人の人数などで手続きが比較的簡単に済むものもあれば、裁判に発展してしまいそうなものまで様々です。費用を支払い専門家に依頼するのか、時間をかけながら相続人自身でするかは人それぞれです。できる範囲は自分で行いながら、難しいところは専門家に依頼する。トラブルを避けるためにも専門家は必要なのかもしれません。