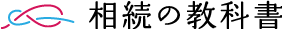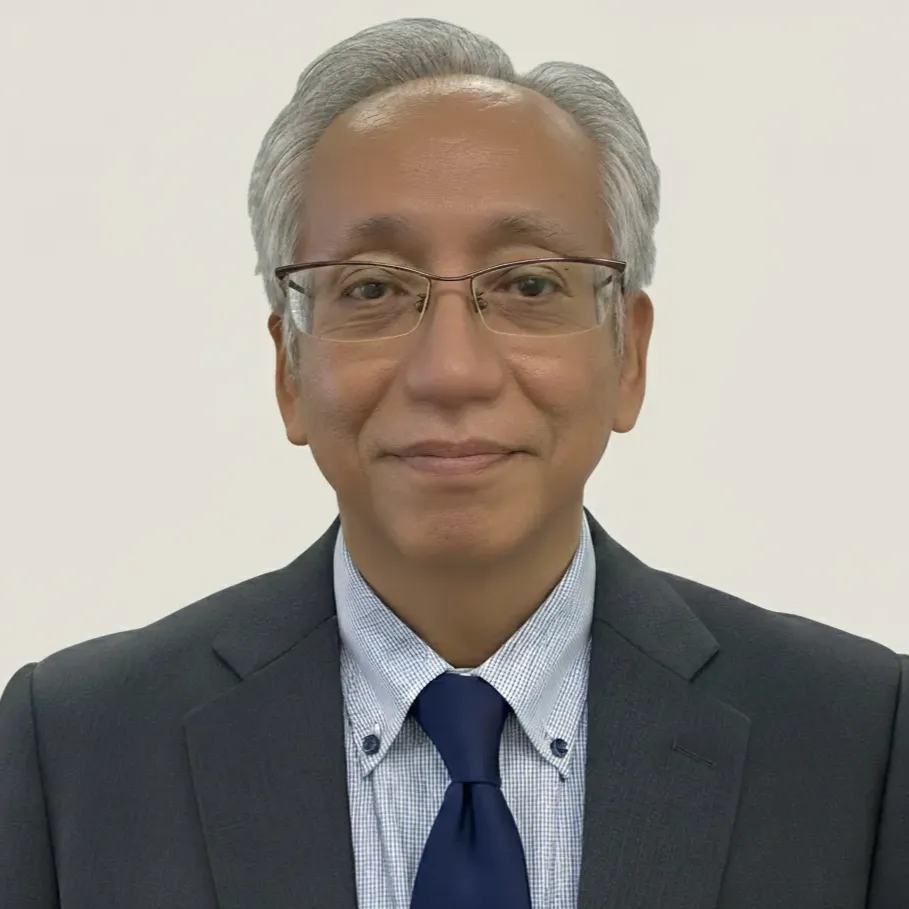相続の対象になるものならないもの|専門家が解説する財産の基礎知識

被相続人が残した財産は、相続できるものとできないものとがあり、相続の手続きも種類により異なります。被相続人が亡くなると、その時点ですべての財産は遺言書がない限り、実質上、相続人全員のものです。今回は、相続できる財産の種類と、それぞれに必要な相続手続きについてみてみましょう。
遺産相続は誰にでも訪れます。急に相続人になった場合でも、この区別がついていれば焦ることなく、少しでも円滑に手続きを進められるかもしれません。また、相続できるものは相続税課税の対象になるものですので、そういった意味でも覚えておいて損はないでしょう。
遺産相続できるもの
・不動産(土地・建物)
・現金、銀行の預金、小切手
・株
・社債
・投資信託などの有価証券
・家具
・自動車
・貴金属
これらは目に見える財産なためわかりやすいですが、著作権・ゴルフの会員権・特許権損害賠償請求権・賃貸権(借家・借地)など、目に見えない財産も相続財産に含まれます。見落としがちで注意が必要です。
相続できるものにはマイナスの財産も?
財産はご自分にとってプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。例えば、借金です。特に連帯保証人になっていたことを身内同士でも知らない場合があります。また、亡くなっても連帯保証責務は消滅しません。そのままの状態で相続人に相続するという形になってしまいます。
相続できない財産とは
その人だけが、持っている権利や資格などです。これを一身専属権といいます。例えば生活保護の受給権や扶養の請求権、雇用されていたところでの地位など、これらは被相続人が個人で条件を満たしていた権利です。こういったものは引き継げません。
生命保険について
相続財産かどうか悩むものに生命保険の保険金があります。これは、被相続人が個人に対して直接渡す財産です。そのため、相続財産ではないとされています。また死亡退職金などがある場合も生命保険金同様、受取人固有の財産とみなされ、相続財産となりません。ただし、相続税を計算するときは「みなし相続財産」として課税対象となります。
最後に
このように個人の権利などは引き継ぐことは出来ず、また個人的に受け取る財産も相続財産という枠には分類されません。しかし、課税の対象にはなるので、そういった部分には注意が必要です。相続は他人ごとのように思っていても、誰にでも実際は起こり得ることです。あらかじめ知っていることで、慌てず対処できることもあるのではないでしょうか。