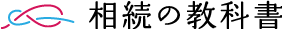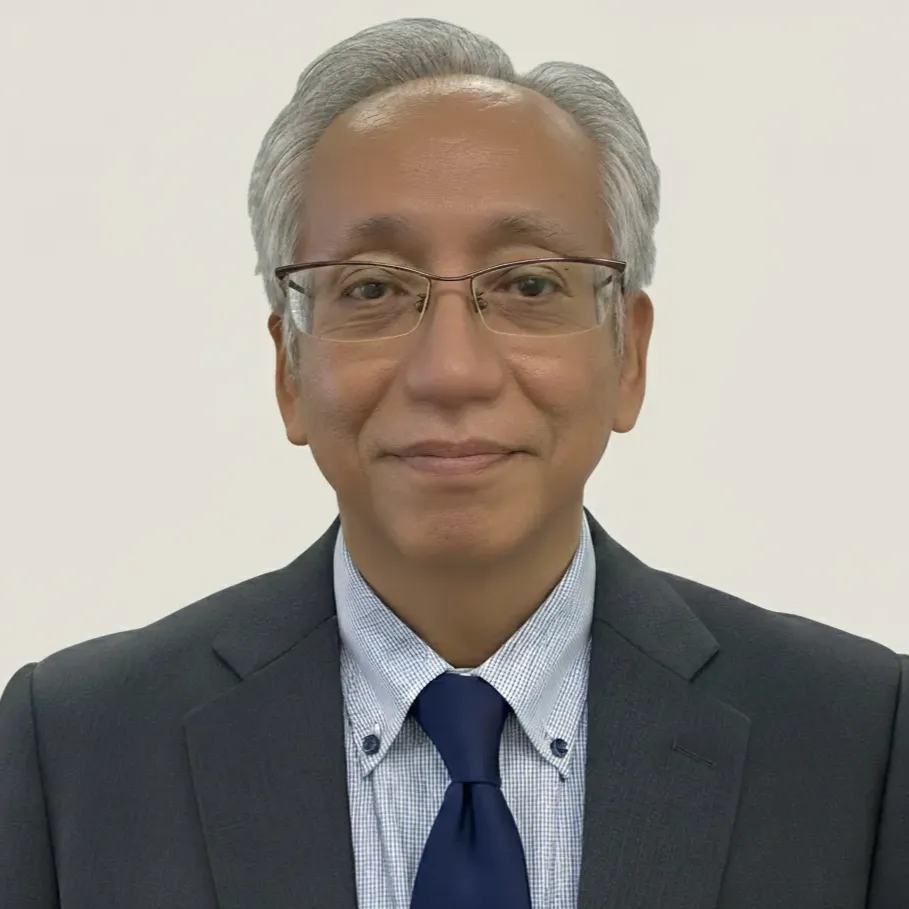金融資産の相続税評価額はこう算出する|種類別の計算方法

日本人は特に貯金をしている人が多いと思います。人によっては公社債(国や地方公共団体、会社などが投資家からお金を借りる際の借用証書)や貸付信託などの利益を受け取るために、受益証券と呼ばれているものを持っている人もいます。もちろんこれらの金融資産も相続の対象であり、相続税の計算をしなければなりません。
今回はこの金融資産の評価方法を説明したいと思います。
預金・貯金について
銀行にお金を預ける際に、普通に預ける普通預金と、利息が少し高く一定期間出せない定期預金などのサービスがあります。さらに、既経過利息と呼ばれている解約時に支払われる利息がついているサービスもあります。
定期預金の多くは既経過預利息がつきます。評価の際は既経過利息も加えて評価しなければなりません。
評価額 = 預入金額 +( 既経過利息 - 源泉所得税額 )
一方で、普通預金など既経過利息が少額なものは、その預入していた金額が評価になります。
受益証券について
受益証券は、貸付信託や証券投資信託などをする際の利益を受け取る権利が記載してある証券になります。評価の方法はそれぞれで違ってきます。
<貸付信託>
市場がないため、銀行などサービスを受けた所の買い取り価格が評価額になります。
元本の額 +( 既経過収益の額 - 源泉所得税額 )- 買取割引料
<証券投資信託>
上場しているものは上場株式の評価方法になり、決算型のものはまた違う計算が必要になります。それ以外のものは下記の計算になります。
基準価額 - 解約請求した場合の源泉所得税額 - 信託財産留保額・解約手数料
公社債について
発行した団体によって名前が変わってきます(国債、地方債、社債などをまとめて公社債と呼んでいます)。公社債には額面金額があり、満期を迎えれば償還(額面の金額を受取ること)ができ、所持している間は利息を貰えます。この一定期日ごとに利息が貰える公社債のことを利付公社債と呼んでいます。
他には割引公社債や転換社債型新株予約権付社債と呼ばれているものがあります。
割引公社債は額面金額から利子相当額を引いた価格で発行されるものです。
転換社債型新株予約権付社債は条件がありますが、いつでも株券に切り替えることができるものです。もちろん通常の公社債と同様に償還や利息なども受けられます。
公社債の評価はそれぞれで変わってきます。さらに社債の場合は上場しているか上場していないかも関係してきます。
<利付公社債>
金融商品取引所に上場されている利付公社債
最終価格+(既経過利息額-源泉所得税額)
日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)
課税時期の平均値+(既経過利息額-源泉所得税額)
それ以外のもの
発行価額+(既経過利息額-源泉所得税額)
<割引公社債>
上場しているもの 最終価格
日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債 課税時期の平均値
それ以外のもの 発行価額+(額面金額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還日までの日数
<転換社債型新株予約権付社債>
上場もしくは店頭登録されているもの 最終価格+(既経過利息額-源泉所得税額)
上場もしくは店頭登録以外のもの・発行会社の株価が転換価格を超えるもの 発行会社の株価×100円/転換社債の転換価格
それ以外のもの 発行価額+(既経過利息額-源泉所得税額)
金融資産も相続税の対象です
金融資産には様々な形があり、それにより評価の仕方が変わるため、間違えて計算をしてしまう可能性があります。間違えたまま評価をし、相続税の申告をすると、後に修正申告をしなければならない状況になる可能性があるので、もしわからないことがあれば専門家に相談してみるといいでしょう。