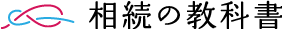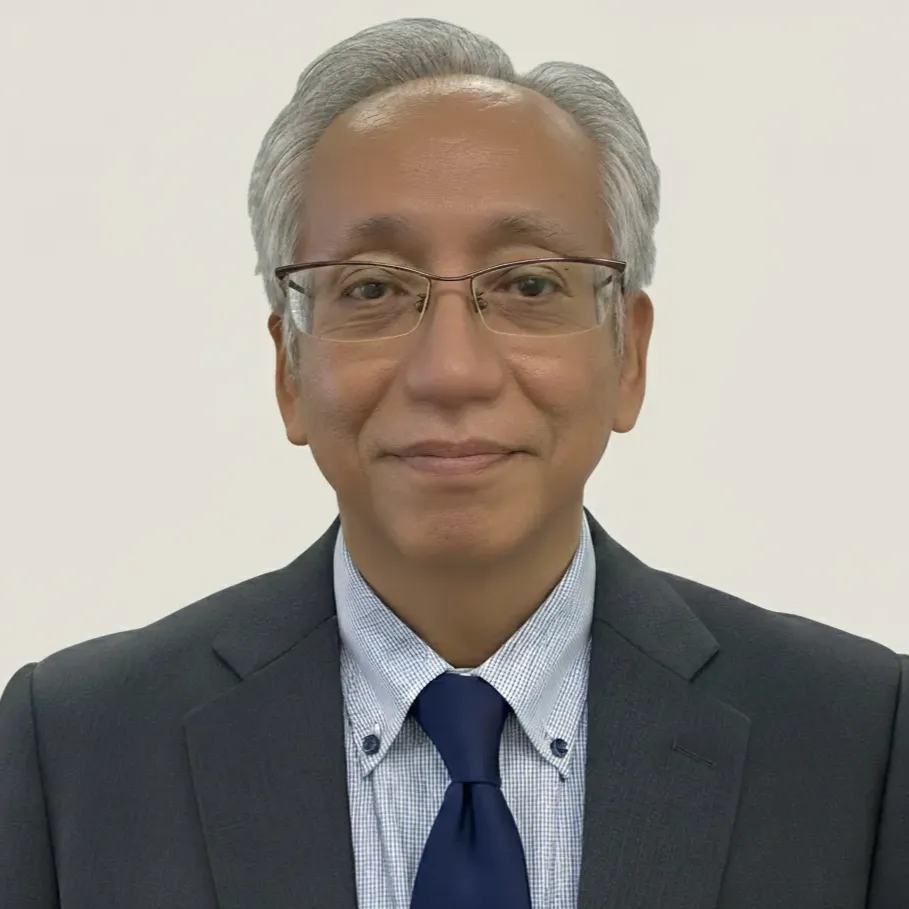固定資産税評価額から考える相続対策|自宅と貸家の建物査定のポイント

土地を持っている人は、その土地の上に自身の住まいを建てる人もいれば、家賃収入を得る為にアパートやマンションを建てる人もいます。家やマンションなど貸家の建物部分も財産と扱われ、名義人が亡くなれば相続税がかかります。そのため、自宅や貸家の建物部分も評価をしなければなりません。
今回は自宅や貸家の評価の仕方についてご説明致します。
評価について
自宅や貸家の建物部分は固定資産として扱われ、毎年固定資産税を支払っています。固定資産税を計算するためには評価を出さなければなりません。この評価は相続時の評価にも使われます。
自宅について
完成されている自宅は固定資産税評価が相続時の評価になります。しかし、自宅を建設中にその自宅の名義人が亡くなるというケースもあります。その場合は、少し評価の仕方が変わり、今までの建設にかかった金額を評価時点の価額に引き直した額の70%が評価になります。人によっては門や塀、庭付きの自宅を持つ人もいますが、この門や塀、庭の施設も評価が必要になります。
門や塀の場合
同じ門や塀などの設備を新しくもう一度同じ場所に作るとしたらかかる費用(再建築価額といいます)から減価償却費を引いた額が評価になります。
※減価償却とは
高額なものを取得した際、その年に一気に費用とするのではなく、購入したものの耐用年数に応じて少しずつ費用としていくことです。
庭園施設
最近の家は大きな庭がついていることが少なくなっていますが、昔からの家では庭も広く作られている所もあります。綺麗な庭を保つにはそれなりの設備が必要になり、その設備も財産として扱われるため評価をしなければなりません。評価の仕方はその設備と同等のものを購入する際の金額の70%が庭園施設の評価になります。
賃貸マンションやアパートについて
貸家を借りて使用をする人の権利は借家権と呼ばれています。この借家権は相続の対象にはなりませんが、借家権割合はその貸家の評価に使われます。借家権割合は30%と設定されているので、その借家権割合を引いた70%がそこの貸家の評価になります
固定資産税評価額×(1-借家権割合)=評価額
貸家を所有している人の中には、その貸家の一部を自身で使い、残りを貸している人もいます。その場合は自身が使っている部分の評価と貸している部分の評価を2つ出さないといけません。
実例として、Aさんから「2000万円の固定資産税評価になっている2階建てのアパートを所有し、1階をAさんが使い、2階を貸している場合の評価はいくらなのか」というそう相談がありました。Aさんが使っている部分と貸している部分の評価を出さないといけないので、それぞれで計算をします。
自用部分 2000万円×1/2=1000万円
貸家部分 2000万円×1/2×(1-0.3)=700万円
これにより自用部分は1000万円、貸家部分は700万円と評価ができました。
相続発生前に、自宅や借家の評価額を算出することの重要性
自身で評価をする場合は、土地と建物を別々で評価をしないといけないため、しっかりと覚えておかないとどちらかの評価をするのを忘れてしまう可能性があります。さらに建物を自身で使うか貸家として使うかで、評価の仕方も少し変わってくるので注意が必要です。評価の仕方があっているのか等の不安があれば、専門家に相談するといいでしょう。