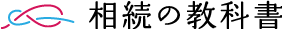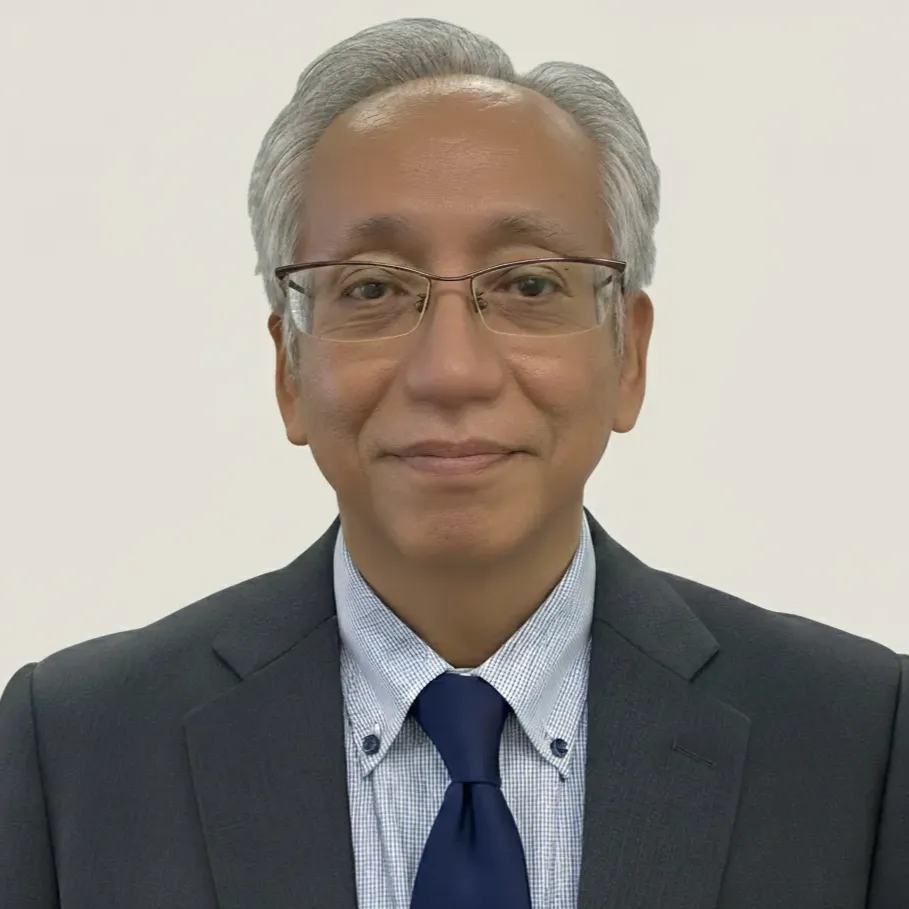遺言書の相続で損をしないために|遺留分請求の基礎から対応まで

遺言書をいつ書くのか、考えたことはありますか?「遺言書を書くほど財産を持っていないから関係ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、後々に残された子供たち同士が、相続が原因で揉めることを防ぐためにも、最低限の遺言書に関する知識は持っておくべきです。
遺言書はどんなものでも有効か
もし親が遺言を残して亡くなったとします。その遺言が正式なものであれば、たとえその遺言の内容に納得いかない場合でも、遺言書に記載されていることが優先されます。しかし、遺言を残す方法にもいくつかの方法があり、遺言を見つけた際の開封にも気をつけなくてはいけない場合があります。記載内容に不備があると無効になってしまうこともありますので、遺言を残すときは注意が必要です。
遺言書の内容に納得できないとき
法定相続人が最低限受取ることが出来る財産は定められています。これを「遺留分」と言います。財産の相続は被相続人の意思を尊重し、遺言などの残されたものに従って行われるべき行為です。しかし、残された家族の生活を護る意味で遺留分という考えが認められています。もし、1人にすべての財産を渡すように指定されていたとしても、法定相続人は少なくとも遺留分に相当する額を受けとる権利を求める申し立てを行うことができます。
遺留分の請求をするとき
遺留分の請求するときは、まずは相手方の間での交渉となります。通知はもちろん口頭でもいいのですが、時効前に遺留分の請求を行ったことを証明するには、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を郵送します。
話し合いでも解決しなかった場合
その場合は家庭裁判所での調停になります。調停で解決しない場合は、訴訟へと移行します。
遺言書に納得いかない場合は「遺留分」を活用できます
複雑な調停までの書類作成など専門家のサポートを得ることで時間と手間を省くことが可能です。
遺言を作成するにしても、遺留分の請求を行うにしても、それぞれどのような専門家に依頼したらいいのかは事前に知っておいてもいいのではないでしょうか。