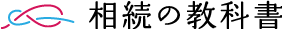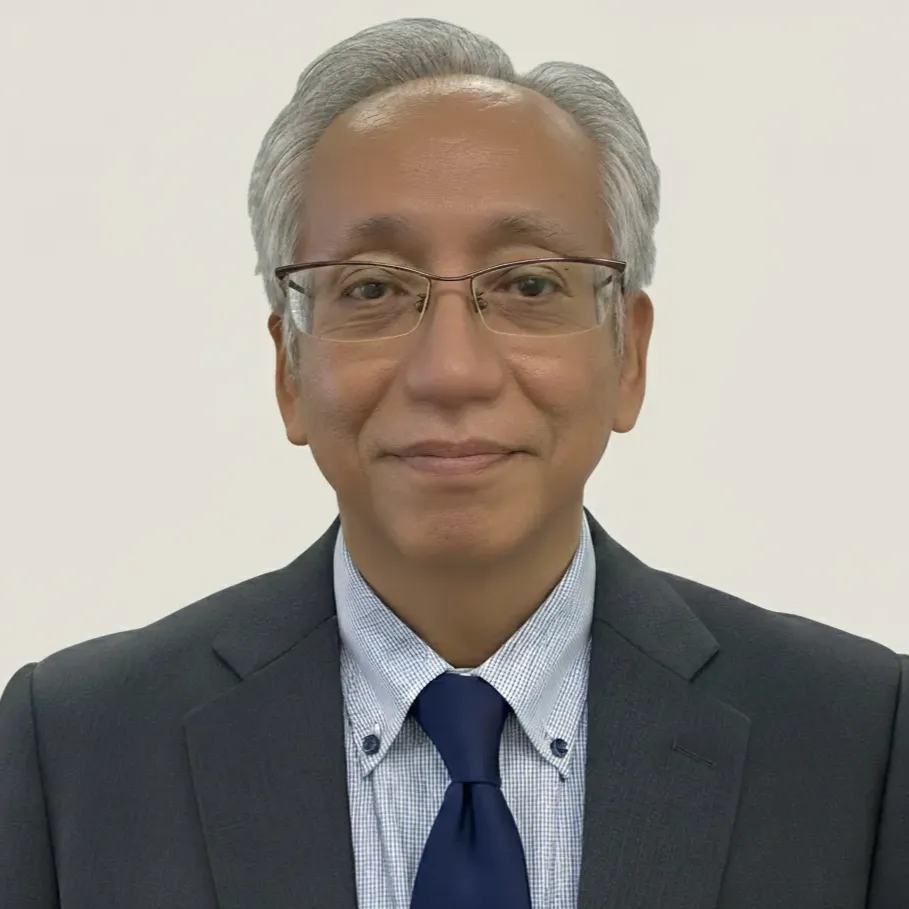遺産相続の基本から解説|遺言書の重要性と法定相続人の決め方

皆さんは、遺言書を書いておこうとお考えですか。「譲る財産はほとんどないから必要がない」などと考えている方も多いのではないでしょうか。では、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合の相続財産はどうなるのでしょうか。今回は、相続について少しご説明致します。
被相続人とは
被相続人とは、遺産相続において相続財産を遺して亡くなってしまわれた方のことを言います。遺産相続は、被相続人の死亡と同時に開始され、相続人に引き継ぐ相続財産は、被相続人が生前に有していた一切の権利義務が対象となります。
相続人とは
被相続人の財産を受け取る人を相続人と呼びます。配偶者や子であっても、例えば相続を放棄した場合などは相続人となりません。また、基本的に遺産相続は被相続人の意思が尊重されるようになっています。
被相続人の意思が尊重されます
被相続人が遺言を残していた場合は、基本的には被相続人の意思が尊重されます。遺言を作り、書かれた遺言が法律で条件が満たされていれば遺言書の内容が尊重されます。また、被相続人により相続人から廃除された方は相続人になることは出来ません。これも相続人の意思を尊重する方法のひとつとなっています。
法定人について
民法で相続権を有すると定められている人を法定相続人といいます。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。遺産分割の順番は法律により決まっており、配偶者は常に相続人となります。次に被相続人の子が相続人となりますが、亡くなっている場合にはその子どもが相続人となります。
また、胎児の場合でも生きて生まれれば相続人とします。子がいない場合などは父母や祖父母が相続人になります。さらに上記に該当するものがいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるなど、相続人の遺産分割の順番が定められています。
最後に
相続の分割方法は全ての相続人が集まって話し合うことにより決められます。話し合いで決まらなかった場合には、裁判や調停で決めなければならなく場合もあるでしょう。
なかには遺言書が作成されていたことによって、スムーズに相続を終えることができたり、受け取る順番が変わったことで揉めてしまったりする場合もあるようです。相続発生時は、被相続人が亡くなったことで、ご家族の気持ちも沈んでいます。残されたご家族が揉めてしまわないように、事前に準備しておくこともご家族への愛情のひとつといえるかもしれません。