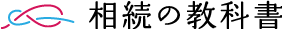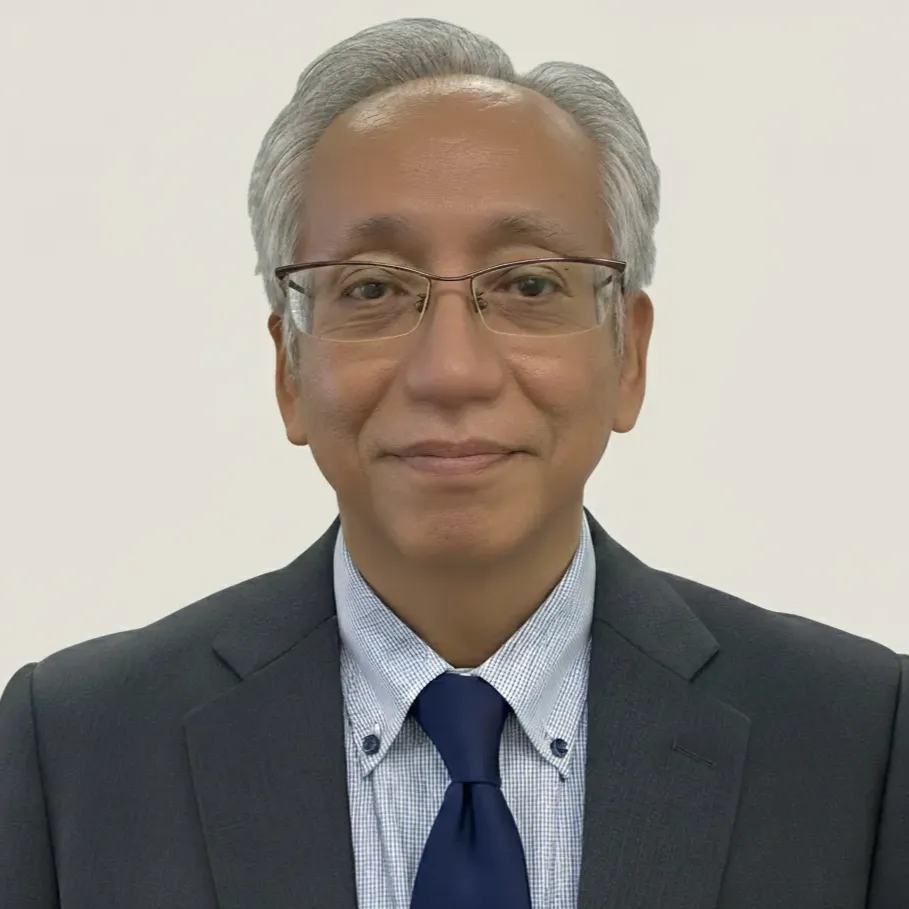自宅建て替えで相続税を抑える|賃貸併用住宅の活用と特例制度

「相続」というものは、財産を持っている限り避けられません。持ち家を活用する方法はないかと相談をされる方も多く、これらを上手く活用する事によって節税対策も可能です。
今回は相談に来られた田中さんの実例を交えてご説明致します。
<田中さん(長女)のケース>
田中さんの父親が亡くなり、相続財産として実家とその近くにある月極駐車場がありました。今回の相続で税は、配偶者の税額の軽減の範囲内に収まりそうだったので、母親が全て相続することになりそうでした。配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が取得した遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。相続税の申告期限までに遺産分割協議書の写し等の必要書類を添えて申告書を提出することが要件となります。
しかし、よく調べてみると母親の納税は回避することができても、母親が亡くなった時、長女の田中さんが相続する際に発生する相続税に対して不安を覚えたそうです。
実家の状態を確認
田中さんは将来的に家を持つことはあまり考えていない様子で、尚且つ実家を建ててからかなりの年月が過ぎているので、いろいろと修繕が必要な箇所がが出てきているようでした。 田中さんも母親も新しく家を建て直すということは難しいという考えだったので、一戸建てではなく賃貸住宅と田中さんらが住む自宅を併用した物件を建てるのはどうかとご提案しました。
賃貸物件を建てるメリットは?
賃貸物件も一戸建ても、同じように固定資産税は発生します。建て直すのには費用も掛かります。しかし賃貸の場合は、上手く部屋の管理ができれば空室を無くすこともでき、そこの入居者からの家賃収入も視野に入れる事ができますし、家賃収入から固定資産税を払うこともできます。もちろんメリットはこれだけではなく、賃貸併用住宅を建てることによって貸家建付地としてその土地の一部を評価できます。
<貸家建付地とは>
家屋を賃貸として第三者に貸している場合の、その土地のことです。
田中さんの場合は自宅との併用となるので、賃貸併用住宅を建てた土地の一部を貸家建付地評価の対象にすることができ、その土地の評価を下げることができます。
<貸家建付地評価とは>
更地の土地と賃貸物件が建っている土地では評価の仕方が違います。
条件を満たせば賃貸物件が建っている土地は貸家建付地として扱われ、その土地の評価を下げる事ができる可能性があります。母親と田中さんは同居もしているため、二人が住んでいる部分は小規模宅地等の特例も受けられる可能性もあります。
<小規模宅地等の特例とは>
被相続人と共に住んでいたなどの条件を満たす場合に、土地の評価を最大80%下げる事ができる特例です。
駐車場の対策
駐車場がアスファルト舗装などされている場合は、建物または構築物の敷地の用に供されているとして貸付事業用宅地等となり、小規模宅地等の特例が適用されます。貸付事業用宅地は200㎡まで50%土地の評価額から減額されます。
最後に
賃貸併用物件を建てることで節税に繋げることが可能です。
今回の田中さんの場合は、自宅の老朽化も進んでいたために自宅を賃貸併用物件として建て直すことで、小規模宅地等の特例と貸家建付地評価とを使うことができました。
しかし、賃貸物件を持つことで空室が出ないように管理しなければなりません。その事に抵抗がある人も中にはいます。専門家に相談することで、その人にとって何が最適なのか等を教えてもらえるので、何か困った事があれば相談するのもいいでしょう。