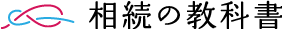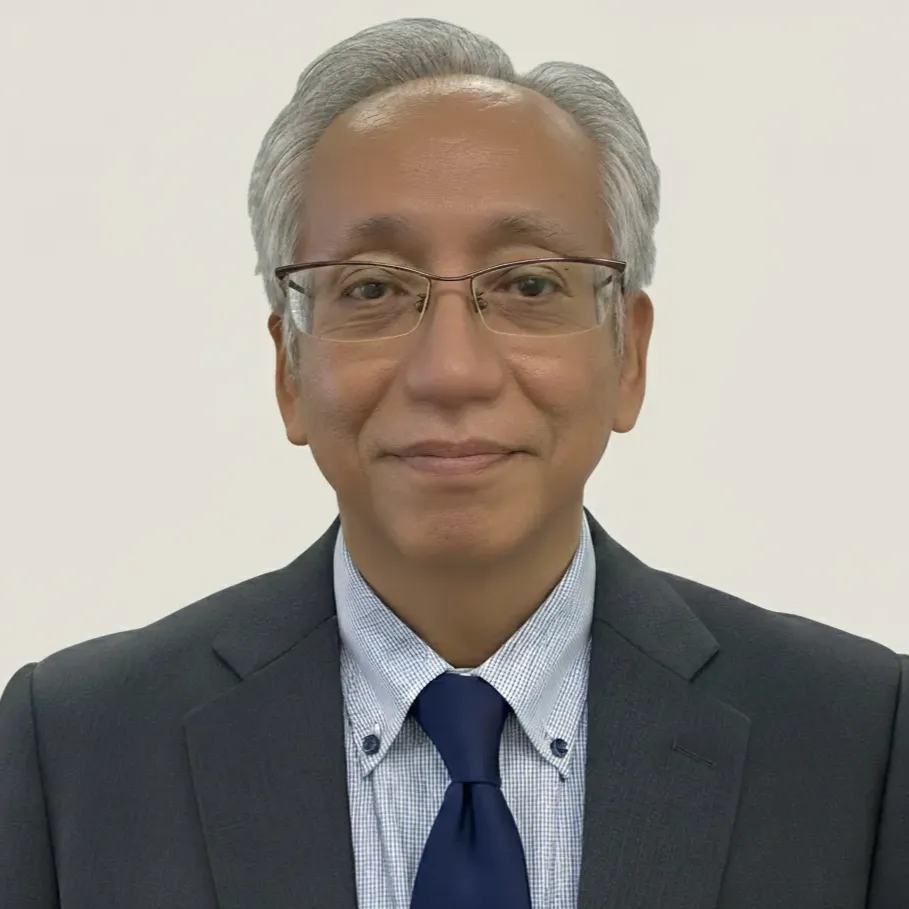財産評価の基本通達とは?各種財産の具体的な評価方法を解説

一言で「財産」といっても様々な種類があり、その評価の仕方で納税義務者間での不公平があってはならないため、国税庁は財産評価基本通達を出しています。この通達には個々の財産の評価の仕方が記載されており、相続税の計算をする際の評価の仕方が確認できます。自動車や家具、電化製品なども財産と扱われ、相続の際は評価をしなければなりません。
今回は土地や株券以外の財産の評価の仕方をご説明致します。
自動車や電化製品などの生活用品について
電化製品や生活用品の購入費はそれぞれで違いますが、年数が経てば劣化していき、買い替えをしないといけない可能性があります。そのため、市場の中古の価格での評価と、市場がない場合においては新品の価格から所有していた年数の償却費を差し引いて評価をします。
ただ、家具や家電の数は多く所有する人もいれば少ない人もいると思います。多く所有している場合はそれぞれ一つずつ評価するのは大変です。ですので、評価が5万円を下回る物は電化製品一式〇〇万円とまとめてもいいと言われています。
骨董品や貴金属について
金やプラチナなどのように市場がある場合は取引価格があるので、課税時期の取引価格で評価ができますが、骨董品やそこまで高価ではない貴金属に関しては鑑定士などに鑑定をしてもらい、その金額が評価になります。
ゴルフ会員権について
ゴルフのプレー料金等の優遇が受けられるゴルフ会員権。株主会員、預託金会員、プレー権のみ等と種類があり、この会員権も財産に含まれるとされているので、相続税の計算の際に評価が必要となります。
会員権は市場で取引されることが多いため、評価の際はその取引価格の70%で評価します。中には入会時に保証金としてお金を預ける預託金制の仕組みを利用しているゴルフ場もあり、その場合の評価は取引価格の70%に預託金の評価を加算しないといけません。
ただ、昔に比べて会員権の価格が下がっているため、中には市場がないものもあります。その際の評価の仕方は、株主会員権の場合は非上場株式の評価できます(預託金制も採用している場合は預託金の評価も加算します)
しかし、預託金制の場合は預託金等の評価がそのまま評価になります。
※非上場株式の評価の仕方は別項で説明します。
預託金の評価
満期を迎えれば預託金が返ってくるため、相続税の課税時期にその預託金が返ってくる場合はその金額が預託金の評価になります。返ってこない場合は請求ができるまでの期間に応じた基準年利率による複利原価の額で評価します。
プレー権のみや譲渡できない会員権の評価は0円となります。
定期金について
定期金とは、年金のように定期的に貰える債権のことです。この定期金も相続の対象となるため、評価を出さないといけませんが、条件によって違います。
受給が始まっていない場合
解約返戻金の金額で評価します。これは生命保険契約を相続日に解約した際の評価方法と同じです。
受給が始まっている場合
・解約返戻金
・一時金があるならその相当額
・1年間に受けるべき金額の1年あたりの平均額を基に一定の方法で計算した金額
この3つの中で一番高いものが評価になります。
財産の評価方法の違いを知ることで、相続手続きの進め方がみえてきます
財産によって評価方法が違うことを説明しました。市場があれば自身でも計算はできますが、専門家に依頼しないと計算が難しい財産もあるので少し注意が必要です。専門家に依頼をすれば比較的楽に評価ができるため、何か分からない事や気になることがあれば相談するのもいいでしょう。