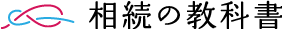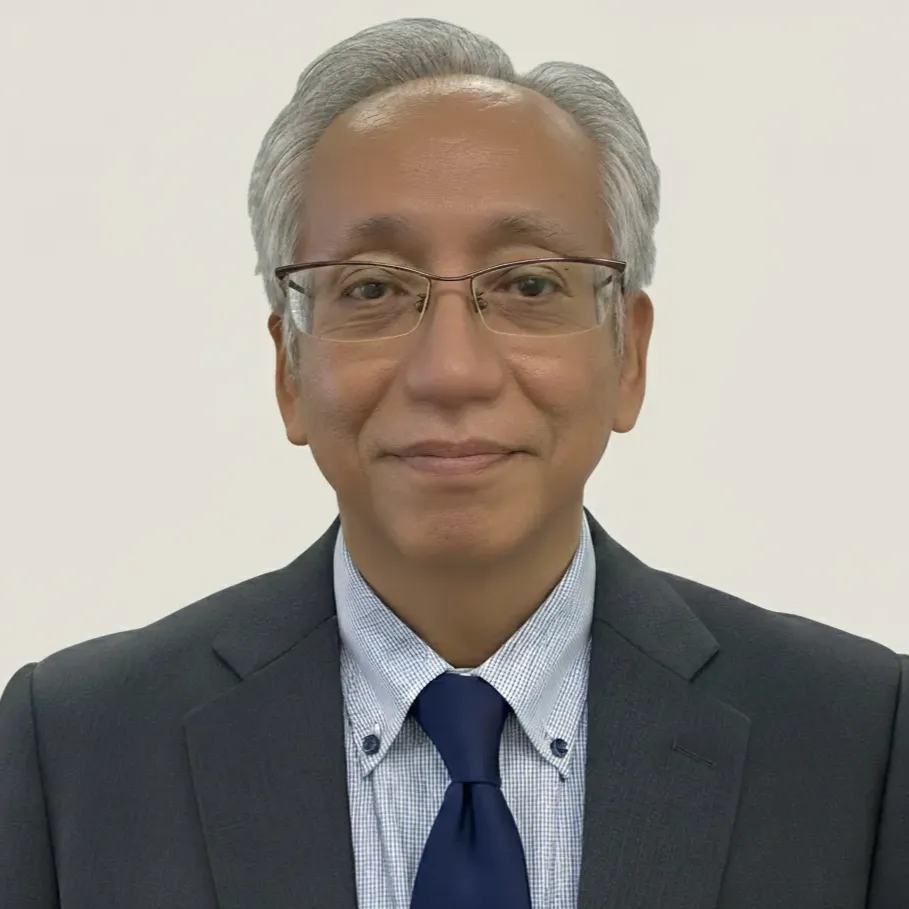遺留分侵害額請求とは?相続人の権利と時効について詳しく解説

相続について調べてみると、普段では聞かないような言葉をたくさん耳にします。相続について知識のない人にとっては言葉ひとつを深く知ろうと頑張っても、手間と時間が掛かります。しかし、知らないでは済まされないこともあります。なるべく少しでも知識として知っておくために、今回は、相続の中でも「遺留分侵害額請求」についてみていきましょう。
遺留分とは
法定相続人は、民法上、一定の割合で相続財産を受け継ぐことができると定められています。この割合のことを「法定相続分」といいますが、法定相続分は絶対というわけではありません。被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる遺産の配分を決めておくことができるからです。
では、遺言書によって遺留分の権利が侵害された場合はどうなるのでしょうか。
例えば兄弟の親が亡くなったときに、兄にしか遺産を相続しないという遺言書が見つかったとします。この場合、弟の方には相続分はありません。遺言が適切なものであればたとえ法定相続分と異なる遺産の配分の割合を定めていたとしても、それは有効となり法定相続分よりも遺言の方が優先されるのです。
こういった場合に遺留分の権利が侵害されたという状態になります。このような場合、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の支払を求めることができます。しかし、相続人でも遺留分がない場合があります。そういった場合はどんな状態なのでしょうか。
被相続人の兄弟、姉妹には遺留分侵害額請求権はない
本来、遺留分というものは最低限の遺産を保障するためのものです。そうすることで、相続人の生活保障が行えると考えられているからです。このような考えから、被相続人の兄弟姉妹は、大半の場合、被相続人とは別に生計を立てていると考えられ、遺留分は必要ないという考えになっています。
また、相続放棄をした場合は、相続人が被相続人のすべての財産、不動産や権利また債務などを受け継ぐことを放棄しているので、遺留分侵害請求を行うことは出来ません。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年を経過したとき、また相続開始から10年経過したときに時効となります。
遺留分侵害額請求は相続人全員に認められているものではありません
遺言書によって遺留分が侵害されたと考えたときは、遺留分侵害額を請求してもよいでしょう。ただし、この遺留分侵害額請求は強制ではありません。ご自身で考えて、裁判所に申し立てることによってはじめて行えることになりますので覚えておくとよいでしょう。また、遺留分侵害額請求には時効があるため、お悩みのときは早めに専門家に相談されることをお勧め致します。