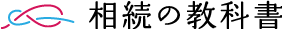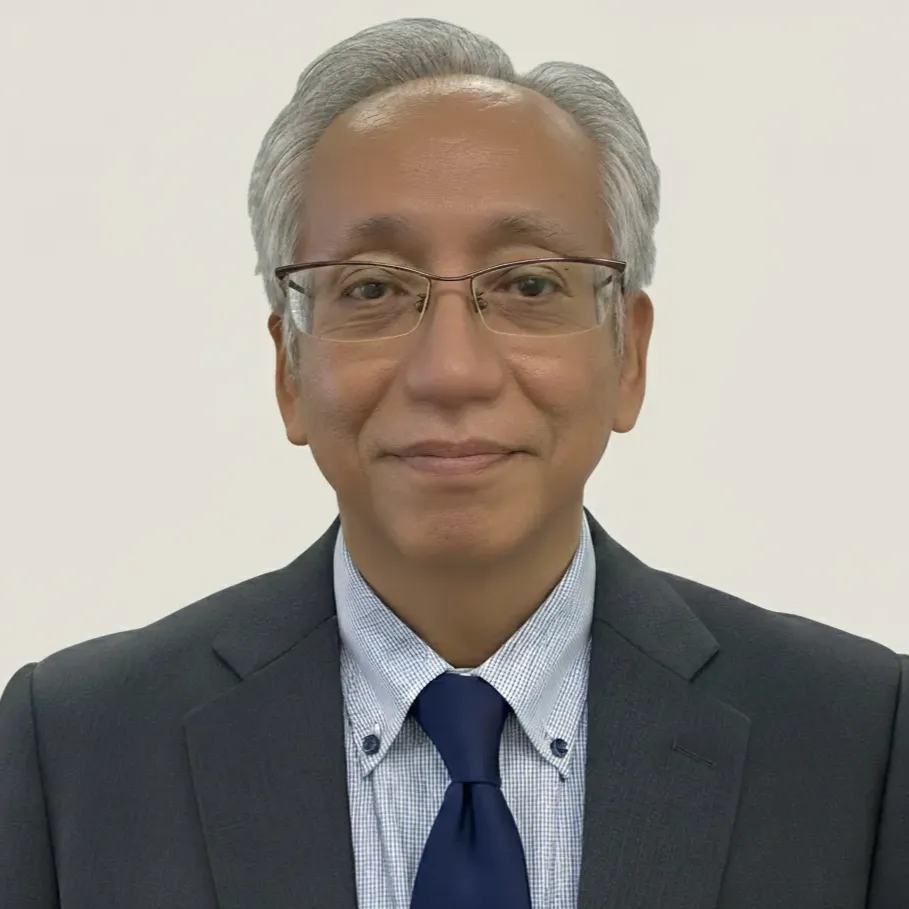遺言による他人への遺産相続|包括遺贈と特定遺贈の違いを徹底解説
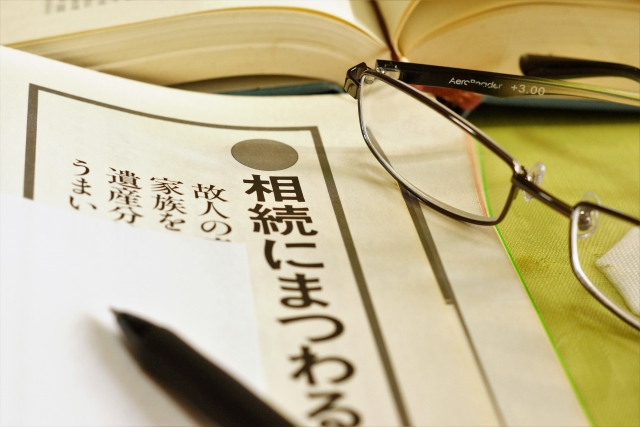
亡くなった被相続人の遺言が見つかり、全く血縁関係のない赤の他人に遺産を相続すると書いてあった場合は、財産を相続することは可能なのでしょうか。もし可能だった場合、どういった手続きをしなければならないのでしょう。今回は、血縁関係のない他人が相続する場合についてご説明致します。
他人が財産を相続できるのか
相続の原則として相続財産は法定相続人に受け継がれます。しかし、法定相続人に相続させたくない場合や、第三者に相続させたい、相続させなければならない場合もあります。そこで、法律で法定相続人以外の第三者に財産を譲ることが可能になる遺贈という制度が設けられています。また遺贈にも包括遺贈と特定遺贈との二種類があります。
第三者の他人でも受け取ることのできる遺贈とは
「遺贈」という制度は、遺言等で第三者の他人に財産を譲り渡すということをいいます。具体的には、遺言などに書く場合でも「他人のAさんを相続人にする」という書き方ではなく、「Aさんに○○の財産を遺贈します。」と記載します。このように書けば第三者に対して財産を譲り渡すことが可能になります。そして遺贈は誰に、何を、どのくらい、と決めることができます。ただ、遺言者が死亡する前に受遺者が亡くなった場合の遺贈は無効となります。
遺贈と相続の具体的な違い
遺贈は遺言で財産の一部または全部を相続人もしくは相続人以外の第三者に無償で贈与することです。相続とは相続人のみに対して行われることです。相続人以外の第三者にも遺産を譲り渡せるのが遺贈、相続人にのみ遺産を渡すのが相続と覚えておくと良いでしょう。
包括遺贈と特定遺贈の主な違いについて
<包括遺贈>
遺産を譲る際、割合で渡すことを包括遺贈といいます。例えば全財産を贈与する、遺産の半分を贈与するという書き方になると包括贈与になります。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法で定められています。 しかし相続人ではないため、遺留分や代襲相続がない等、相続人とは異なる点もありますので注意が必要です 。
<特定遺贈>
「土地を贈与する」というように、指定した財産を遺贈することを特定遺贈といいます。包括遺贈との違いは、債務を引き継がない、遺産分割協議に参加しない等の点です。
最後に
相続人以外が遺産を受け取ることは可能です。相続人以外の人が遺産を受け取るときには遺贈になります。また、遺贈の中にも種類があるので、もし遺贈を検討するのであれば専門家に相談されることをお勧めいたします。