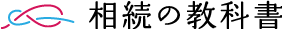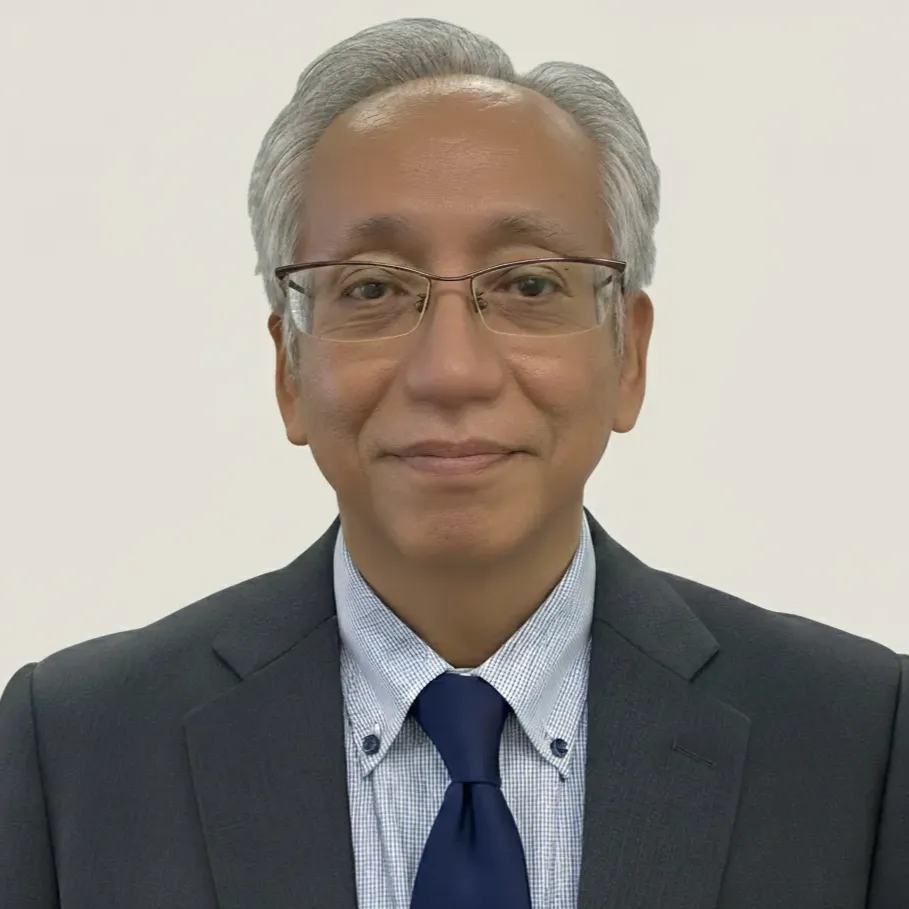遺言書の基礎知識|種類選びで失敗しない3つの証書の特徴と違い

法定相続分は法律により定められています。しかし、被相続人が一部の相続人に多く相続させたい、もしくは少なく相続させたいという場合もあります。そんな時に遺言書を残すことで相続財産の分割の仕方を指示することができます。
遺言の効力について
遺言に書いてあることは原則その通りにする必要があります。しかし、遺言の対象にできないものもあるので注意が必要です。遺言書では、相続人や法定相続分に関して、誰に・何を・どれだけ分けるのか指定ができます。仮に第三者に遺贈したいと書いてあるならその人が相続人でなくても遺産を分けることが可能になります。しかし、相続には遺留分という制度があり、これは「一部の法定相続人に最低限の相続分が保障されている」という制度です。そのため、遺言で相続させないと書いてあっても、遺留分は相続させることとなります。
遺言書の形式
遺言書にも様々な形式があり、それぞれで作成の仕方が違います。
◇公正証書遺言
公証人が遺言者から内容を聞き取る等をして遺言書を作成します。公証人と遺言者は、手続き当日2人以上の証人の前で遺言の内容を確認します。書面は3通作成され、1通は公証役場で保存、あとの2通は遺言者に渡されます。
<メリット>
・無効になりづらい
・保存は公証役場なので偽造や紛失がほぼない
・裁判所の検認が必要ない
・文字を書けなくても利用可能
<デメリット>
・時間と費用がかかる
◇自筆証書遺言
遺言者が好きなタイミングで書くため、気持ちが変わった場合に修正が可能です。
<メリット>
・費用がかからない
・修正が可能
・遺言者が保存するので秘密にできる
<デメリット>
・書き方を間違えると無効になる
・紛失や発見されない可能性がある
・裁判所の検認が必要となる
・財産目録以外は自筆で書かなければならない
◇秘密証書遺言
遺言者が作成をし、封をしたものを公証人に渡します。公証人はそれを確認し封紙に署名します。開けられた形跡があるものは無効となるので注意が必要です。
<メリット>
・内容は遺言者しかわからないので秘密にできる
・偽造や変造の恐れがない
・署名と捺印ができるなら代筆を頼んでも大丈夫
<デメリット>
・証人が2人必要
・保管は遺言者となるので遺言書を発見されない可能性がある
・内容に不備がある場合無効になる恐れがある
・裁判所の検認が必要
最後に
今回は簡単に遺言書の種類について説明してみました。遺言書は非常に便利なものです。しかし、書き方を間違えると無効になってしまう可能性や、遺言では残せない内容などもあるので注意が必要です。遺言書作成について悩んでいる場合や、どんな内容の遺言をどの形式で作成するか困っている場合などには、トラブルを防ぐためにも一度専門家に相談してみることをお勧め致します。